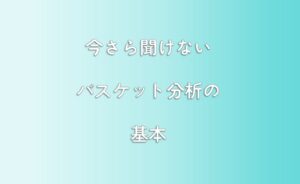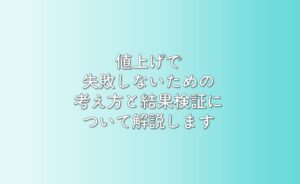【コラム】消費者アンケートの有用性と注意点を解説~顧客を知り、マーケティングに活かすには
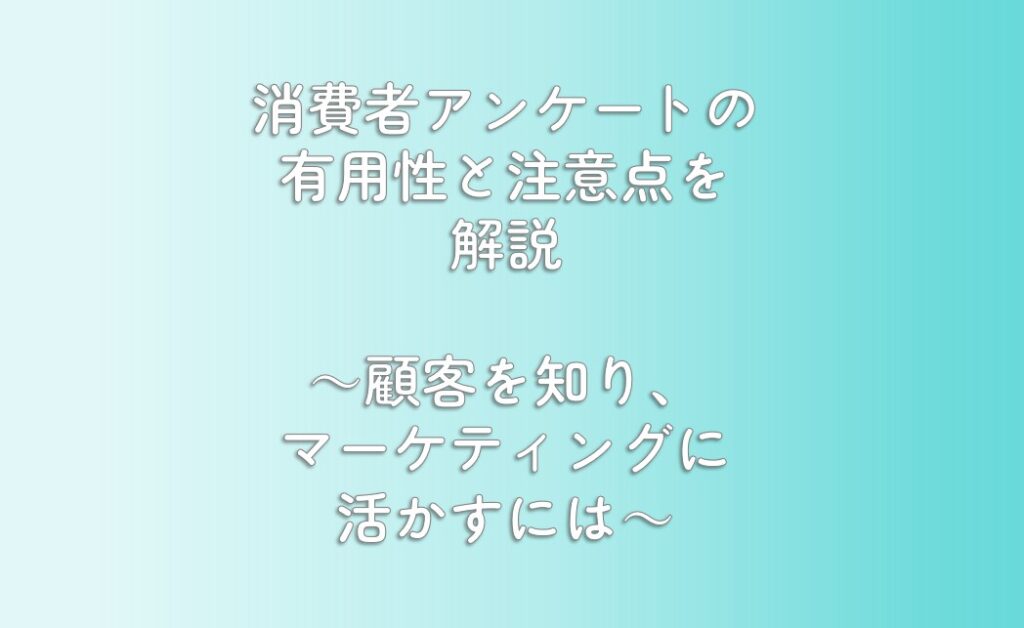
顧客を知ることはビジネスの基本ですが、そのために実施されることが多いのが消費者アンケートです。
現在では、インターネットを通じて簡単に消費者アンケートを実施することができるようになっているので、普段の業務でアンケートを実施している方もいることでしょう。しかし、専門知識やスキルを持たない人が、調査設計(アンケート設計)を、見様見真似で行ってしまうと、回答者が答えづらいアンケートになったり、得られた回答データが使い物にならないこともあります。
そこで、このコラムでは、身近な調査手法である消費者アンケートの有用性と注意点を解説します。
※この記事は2025年3月に市川マーケティング研究所の鈴木雄高が執筆したものです。
目次
1.はじめに
消費者アンケートは、顧客のニーズや意識を把握するための重要なツールです。適切なアンケート設計と分析を行うことで、マーケティング戦略の策定や商品・サービスの改善に役立てることができます。
しかし、アンケート調査は、その設計や実施方法によっては、期待した結果が得られない可能性もあります。また、アンケート調査以外にも顧客を知るための優れた方法があるため、アンケート調査が他の方法に比べて優れた点や劣っている点を知ることも欠かせません。
本コラムでは、顧客を知るための方法として、消費者アンケートの特徴を紹介した上で、実施する際の注意事項を解説します。
2.顧客を知るための方法6選~消費者アンケートとその他の方法~
企業が顧客を知るための方法には、アンケート調査以外にも様々な方法があります。
ここでは、スーパーマーケットの運営企業や店舗を事例に、自社や自店の顧客を知るための方法を6種類紹介します。
.jpg)
図表 1 顧客を知るための様々な方法
出典:筆者作成。
① 消費者アンケート:
店舗での買物体験、商品への満足度、改善要望、他店の利用実態などを直接的に収集します。アンケート調査の回答データを分析することで、顧客ニーズを把握し、店舗運営や商品開発に役立てることができます。
② 消費者インタビュー:
特定の顧客層を対象に、インタビューを実施し、深層心理や潜在的なニーズを探ります。共通する特徴を持った顧客のグループを複数つくり、座談会形式で意見を収集するフォーカスグループインタビュー、消費者と1対1でじっくりと話を聞くデプスインタビューなど、目的に応じて手法を選択します。
③ POSデータ分析:
売れ筋商品、時間帯別の売上、売れ行きの季節トレンドなどを確認し、顧客のニーズを把握することで、品揃えや陳列、販売促進などに役立てることができます。目的に応じて、ABC分析、トレンド分析などの手法を使い分けます。
④ ID-POSデータ分析:
ポイントカードや会員アプリなどを通じて取得した顧客の属性情報をPOSデータに紐づけたID-POSデータを分析します。クラスター分析によって購買の傾向が似た顧客のセグメントを作成したり、バスケット分析で同時購買されやすい商品同士の組み合わせを発見することができます(参考:「今さら聞けないバスケット分析の基本」)。顧客の嗜好やニーズを把握することで、パーソナライズされた情報提供やターゲティング販促などに役立てることができます。
⑤ 行動観察調査:
顧客の店内での行動を観察することで、商品の選び方、販売促進施策への反応、買いづらそうにしている様子などを把握します。顧客の視点に立ち、店舗レイアウトや商品陳列の改善に役立てることができます。調査員が目視で観察する方法の他、売場に設置したカメラで撮影した映像を使用する方法もあります。
⑥ SNS分析:
X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSで、顧客の口コミや反応を分析します。顧客がどのような商品やサービスに関心を持っているか、どのような不満を持っているかを把握します。自社の商品、サービス以外の、どのようなことに関心を持っているかを把握することも可能です。
3.消費者アンケートの優れている点と劣っている点
上述のように、顧客を知るための方法には、消費者アンケートを含め様々なものがあります。他の方法よりも優れているところや、劣るところを踏まえた上で消費者アンケートを実施しないと、調査結果を活用しづらいことや、最悪の場合、無駄になってしまうこともありえます。
そこで、ここでは、消費者アンケートが他の方法と比べて優れている点と劣っている点を確認します。
3-1.消費者アンケートの優れている点
■直接的な声の収集:
顧客が店舗や商品に対して感じている満足度や不満、具体的な要望を直接的に収集できるため、顧客の生の声を知ることができます。
■広範囲な情報収集:
アンケート設計によっては、購買行動だけでなく、ライフスタイルや価値観など、幅広い情報を収集できます。
■定量的なデータ分析:
選択式の質問などを多く含めることで、定量的なデータを収集し、統計的な分析が可能です。これにより、顧客全体の傾向を把握しやすくなります。
■競合他社との比較:
他社(スーパーマーケットであれば商圏内の他店やECなど)の利用状況や評価を尋ねることで、自社の強みや弱みを顧客視点で客観的に把握し、改善に繋げることができます。
3-2.消費者アンケートの劣っている点
■回答者の偏り:
アンケートに回答する顧客は、特定の層に偏る可能性があり、全体の意見を代表しない場合があります。
■回答の質のばらつき:
自由記述式の質問では、回答者の文章力や表現力によって回答の質にばらつきが出ることがあります。
■回答者の記憶や感情による回答のゆがみ:
過去の購買体験に関する質問では、回答者の記憶が曖昧であったり、感情によって回答がゆがむ(バイアスが発生する)可能性があります。
■アンケート設計の難しさ:
効果的なアンケートを作成するには、専門的な知識やスキルが必要であり、時間と手間がかかります。
■回答率の低さ:
アンケート内容や実施方法、回答方法によっては、回答率が低く、十分な量の回答を収集できない場合があります。
4.消費者アンケートの種類
商品やサービスに対する消費者の意見や要望を収集するための調査手法である消費者アンケートには様々な種類があります。それぞれに、長所と短所があるため、調査を実施する際は、目的に合った種類を選ぶことが必要です。
■インターネット調査:
インターネットを通じてアンケートを実施する方法です。時間や場所の制約が少なく、比較的安価かつ短期間で実施できます。対象者は、パソコンやスマートフォン、タブレット端末など、様々な機器で回答することができます。優れた点としては、質問数の多いアンケート調査を実施しやすいことや、回答データの回収から集計を行うまでの時間が相対的に短いことが挙げられます。欠点としては、他のアンケート調査と比べ、いい加減な回答が混在しやすいことがあります。
■郵送調査:
アンケート用紙を郵送し、対象者が回答を記入した用紙を回収する方法です。インターネットを利用しない人の回答を得ることができますが、回収率が低い傾向があります。また、時間や費用がかかる傾向があります。
■面接調査:
調査員が対象者と直接対面し、口頭で質問をして回答を得る調査方法です。アンケート調査の中でも、より深く、詳細な情報を収集する際に有効な手法と言えます。典型的なものに、商業施設や小売店舗の来店者に対して行う面接調査があります。このような場合、調査協力を得るのが難しい場合があること、調査の所要時間を長くできないため質問数を多くしづらい、といった欠点があります。質問紙を使う調査の他、タブレット端末を使用することもあります。
■電話調査:
電話で質問し、回答を記録する方法です。高齢者層など、インターネットを利用しない層にもアプローチできます。ただし、最近は家に電話がない人や、家の電話が鳴っても受話しない人も多いため、思うように回答が集まらない可能性があります。また、限られた時間で調査を終える必要があるため、1人の対象者に対する質問数を多くできません。
5.顧客理解を深めるために実施する消費者アンケート
消費者アンケートは、顧客理解を深めるための有効な手段です。顧客ニーズの把握、潜在的なニーズの発見、顧客満足度の把握など、様々な目的で活用できます。
■顧客ニーズの把握:
消費者アンケートを通じて、顧客が商品やサービスに何を求めているのかを把握することができます。具体的なニーズを把握することで、商品開発やサービス改善に繋げることができます。
■潜在的なニーズの発見:
顧客自身が気づいていない潜在的なニーズを発見したい場合、一般的にはインタビュー調査や行動観察調査などの定性調査を行いますが、アンケート調査でも自由記述式の質問を通じて、潜在的なニーズを探ることは可能です。
■顧客満足度の把握:
消費者アンケートを通じて、顧客が商品やサービスにどの程度満足しているかを把握することができます。顧客満足度を定期的に測定することで、改善点を見つけ、顧客満足度向上に繋げることができます。
6.消費者アンケートをマーケティングに活かす
消費者アンケートで得られた情報は、マーケティング戦略に活かすことができます。商品・サービス開発、顧客ターゲティング、ブランディングなど、様々な場面で活用できます。
-1024x501.jpg)
図表 2 消費者アンケートをマーケティングに活かすまでの流れ
出典:筆者作成。
■商品・サービスの開発に活かす:
消費者アンケートで得られた顧客のニーズや要望は、商品・サービスの開発や改善に活かすことができます。顧客の声を反映させることで、より魅力的な商品・サービスを提供することができます。例えば、顧客満足度と、それに影響を与える要因を分析することで、施策の巧拙が満足度に強く影響する重要なものを明らかにし、その改善に注力することができます。
■顧客ターゲティングに活かす:
消費者アンケートで得られた顧客の属性や価値観、ライフスタイルに関する情報は、顧客ターゲティングに活かすことができます。ターゲット顧客を明確にすることで、より効果的なマーケティングを展開することができます。
■ブランディングに活かす:
消費者アンケートで得られた顧客のブランドイメージに関する情報は、ブランディングに活かすことができます。顧客が自社ブランドにどのようなイメージを持っているかを把握することで、ブランドイメージの向上に繋げることができる他、顧客が競合他社に対して抱いているイメージを把握すれば、自社を差別化された存在として位置付けてもらうために講じるべき施策を検討することもできます。
7.消費者アンケート実施時の注意点
効果的なアンケートを作成・実施・分析するには、いくつかの重要な点に注意する必要があります。ここでは、アンケート調査の実施前(設計)、実施、実施後(集計・分析と可視化)に分けて、注意すべき事項を確認します。
7-1.アンケート設計のポイント
①目的を明確にする:
- アンケートを実施する目的を具体的に設定することが重要です。「顧客満足度を知りたい」「新商品のニーズを把握したい」など、目的によって質問内容や形式が変わります。
- 目的を明確にすることで、必要な情報を効率的に収集できます。
②対象者の条件を明確にする:
- 目的を踏まえて、適切な回答を集めるために、対象者条件を決めます。
- 同業他社や関連企業、関連業界、調査や広告などの事業に従事する人を対象者に含めないなど、対象外の条件を決めることも重要です。
③回答しやすい質問にする:
- 専門用語や曖昧な表現を避け、誰でも理解できる言葉で質問を作成します。
- 長すぎる質問や複雑な質問は避け、簡潔で答えやすい質問を心がけます。
- 選択肢は、回答者が迷わないように、適切に設定します。
④選択肢を適切に設定する:
- 選択肢の数は多くしすぎず、回答者が適切な選択肢を選べるようにします。
- 選択肢の順序も重要です。例えば、「はい」「いいえ」の順序を統一することで、回答者の負担を軽減できます。
- インターネット調査の場合、選択肢の順序が回答にゆがみを与える可能性を除去するために、「その他」以外の選択肢の順序をランダマイズさせることが有効です。
⑤質問の順番を考慮する:
- 質問の順番は、回答に影響を与える可能性があります。
- 簡単な質問から始め、徐々に核心に迫る質問へと進むようにするのが効果的です。
- 関連性の高い質問は近付けて配置すると、回答者の負担を軽減できます。
⑥個人情報保護に配慮する:
- 個人情報を収集する場合は、利用目的を明確にし、適切な管理体制を整える必要があります。
- プライバシーポリシーを明示し、回答者が安心して回答できる環境を提供します。
7-2.アンケート実施のポイント
①回答者に協力を依頼する:
- アンケートの目的や重要性を丁寧に説明し、回答者の協力を得られるように努めます。
- 多くの回答者を集めるためには、回答者への謝礼やインセンティブを用意することも有効です。
②回答しやすい環境を提供する:
対面で行う面接調査の場合、回答者が落ち着いて回答できる静かな環境を提供します。
オンラインアンケートの場合は、スマートフォンやタブレットなど、様々なデバイスに対応させます。
③回答者のプライバシーを保護する:
- 回答者の個人情報や回答内容が外部に漏れないように、適切なセキュリティ対策を講じます。
- 匿名性を保証することで、回答者が正直な意見を述べやすくなります。
④回答期限を守ってもらう:
- 回答期限を明確に伝え、期限内に回答を回収できるように促します。
- 期限が近づいたら、リマインダーを送信するなど、回答を促す工夫も必要です。
7-3.アンケート結果の集計・分析と可視化
①適切な集計・分析方法を選択する:
- アンケートの目的や質問形式に合わせて、適切な集計・分析方法を選択します。
- 回答データの集計・分析方法には、単純集計、クロス集計、統計分析などがあります。
②結果を分かりやすく可視化する:
- 集計・分析結果をグラフや表などを用いて分かりやすく可視化します。
- 表計算ソフトやプレゼンテーションソフトを使用することで、効果的な調査レポートを作成できます。
③結果を解釈し、示唆を得る:
- 可視化したデータを分析し、アンケートの目的と照らし合わせて、どのような示唆が得られるかを検討します。
- データから読み取れる顧客のニーズや課題を明確にします。
④結果を関係者と共有する:
- 分析結果を関係者と共有し、今後のマーケティング戦略や商品開発に活かします。
- 関係者からのフィードバックを得ることで、より深い洞察が得られる場合があります。
8.まとめ
消費者アンケートは、顧客理解を深め、マーケティング戦略に活かすための有効なツールです。しかし、アンケート設計や分析には専門知識が必要です。ぜひ、本コラムで解説したアンケート調査の特徴や注意点を参考に、効果的なアンケート調査を実施してください。