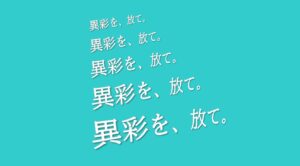【コラム】ボイコットとバイコットはSNS時代に大きな影響力を持つ

3か月前のNIKKEI Asiaに"Boycott-hit US brands in Malaysia and Indonesia scramble to reverse losses"(マレーシアとインドネシアで不買運動の標的となった米国ブランドが、売上減を取り戻そうと必死になっている)と題された記事がありました。
NIKKEI Asia
Boycott-hit US brands in Malaysia and Indonesia scramble to reverse losses(August 14, 2025)
https://asia.nikkei.com/business/consumer/boycott-hit-us-brands-in-malaysia-and-indonesia-scramble-to-reverse-losses
記事によると、イスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザに対する攻撃が続く中、イスラム教徒が多いマレーシアとインドネシアでは、米国系の有名チェーン店に対する消費者の不買運動(ボイコット)が起き、高い人気を誇っていた当地のスターバックス、ケンタッキー・フライド・チキン、ピザハットなどは、メニューの現地化や値下げなどによって対応したり、売上の減少を埋め合わせるために資産を売却するなどしている、ということです。
メニューの現地化というのは、現地食材を使ったメニューを提供することなどですが、例えばマレーシアの首都クアラルンプールのスターバックスで、地元のバリスタが厳選したドリンクのキャンペーンを行うことなども含みます。同チェーンは、他にも、現地のアーティストがデザインしたアイテムを販売することにより、米国色を薄めています。こうした取り組みによって、ボイコットしていた消費者が多少は戻っているそうです。
――という出来事を耳目にすると、世界には、「宗教や戦争とビジネス、消費行動が近い距離にある国があるのだ(日本とは大きく異なる)」と思うかもしれませんね。
では、日本では消費者によるボイコットは起きていないかというと、そんなことはありません。
*****
ここで、改めてボイコットについて説明します。
「ボイコット(boycott)」とは、特定の企業や製品に反対して「購入や利用を控える」行動を指します。「不買運動」と言い換えられます。たとえば、倫理的な問題や社会的な批判を受けた企業に対し、消費者が購入を控える場合です。
日本でも、パレスチナに連帯を示す消費者が、イスラエルを支援している企業を批判するために、その企業の商品やサービスの購入、利用を控えるケースが見られます。
見られます、というのは、文字通り可視化されて私たちが目にすることができる状況にあることを意味します。SNS時代の現在、ボイコットの意思表示が瞬時に拡散されるからです。
SNS上を流れる投稿をつぶさに見ていると、日本でもボイコットをしている人が盛んに投稿していることがわかります(#不買運動 などで検索していてください)。消費者のこうした行動は、(インドネシアやマレーシアで注目されたように)企業の評判や売上に大きな影響を与えることがあります。
単なる個人の選択であるボイコットが、社会的なメッセージとなる点が特徴です。
ボイコットは「嫌だ」という意思を可視化する手段であり、SNSで拡散されることで、共感の輪(反発の輪?)が広がる可能性があります。そのため、企業にとって無視できない影響力を持つ行動となるのです。消費者の価値観や倫理観が購買行動に直結する時代、企業は単に商品を提供するだけでなく、社会やステークホルダーの期待に応える姿勢が求められています。
ボイコットの例:
・世界的な食品メーカーが、児童労働や水資源の不適切な利用・森林破壊などで非難を受け、ボイコット運動の対象になっています。
・米国に本社を構えるシリアルのトップ企業は、原料調達のサプライチェーンで、例えばパーム油由来の森林破壊や児童労働が問題になり、消費者の離反を招いたとの報告があります。
・農業原料や穀物の大手企業は、南米アマゾンなどでの土地権侵害や環境破壊を背景として、市民団体などからのボイコット対象になっています。
*****
なお、消費者が意思表示を示すために不買運動をする「ボイコット(boycott)」に対して、特定の企業・商品・サービスを積極的に購入することで応援や共感を示すことを、「バイコット(buycott)」と呼びます。「応援消費」と呼ぶこともあります。
筆者は、パレスチナに連帯を示す消費者が、現地で栽培されたオリーブを使った製品を購入し、その製品の写真や購入できるECサイトの情報をSNSで発信しているのを目にしたことがあります。
これを読んでいる方の中にも、2011年3月11日に発生した東日本大震災の被災地で栽培された桃や、水揚げされた魚やその加工品を「買って応援」「食べて応援」したことがある人がいることでしょう。
また、少し高額ではありますが、現地の農地、労働者に、少しでも多くお金が届くようにと、フェアトレードのコーヒー豆を購入している人もいるかもしれません。
*****
両者とも単なる購買行動ではなく、意思表示としての消費行動です。SNS時代では、個人のボイコット・バイコットが拡散され、社会や企業に大きな影響を与えることがあります。
冒頭で紹介した、マレーシアとインドネシアにおける米国系チェーン店に対する不買運動が、各社の売上を減らした、というような大きな影響は、2025年の日本国内では見られません。しかし、今後、日本でも同様のことが起きる可能性は小さくないでしょう。その可能性は大いにあると思います。
企業は、ブランド価値や信頼を維持する上で、消費者の期待に応えることが不可欠です。SNS時代では、隠れた不満や支持が瞬時に拡散され、企業戦略に直接影響を及ぼします。
ビジネスパーソンに求められるのは、社会課題や顧客の価値観、自社に期待されていることを深く理解し、そのことを企業の意思決定やマーケティング施策に反映させる視点です。単なる数字や売上の目標だけでなく、社会的な信頼や支持をどのように獲得するかが問われるようになっています。
ボイコットを受けて対応に追われている企業を他人事だと思っていると、ふとしたきっかけで、「○○には期待していたのに、ずっと○○が好きだったのに、私のそんな気持ちを裏切るようなことをした○○の商品は、もう買わない」と、長年の顧客が思うようなことを(自社が)してしまうかもしれません。ボイコット対象となっている国内外の事例を他山の石として学び、自社や自分の行動にどう反映させるかを考えておくことをおすすめします。
*****
更新情報:2026年1月12日に後段二つのパラグラフの言い回しを変更しました。2026年2月20日に誤字を修正しました。